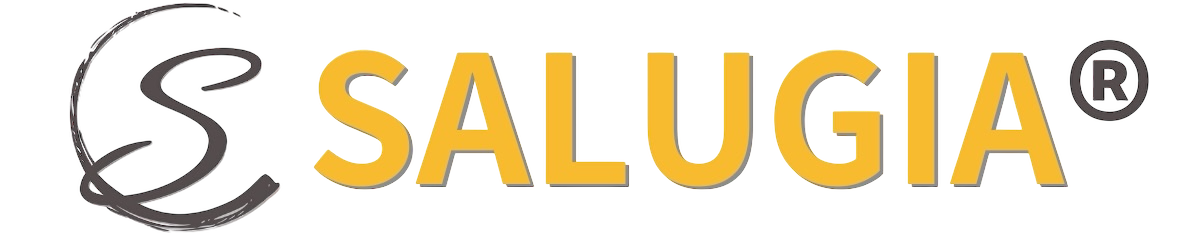食材リスト
目次
食材リスト
炭水化物編
| 食材名 | ◎ | ○ | △ | × |
|---|---|---|---|---|
| 白米 | ○ | |||
| 玄米 | ◎ | |||
| 雑穀米 | ◎ | |||
| もち米 | ○ | |||
| コーン | ◎ | |||
| オートミール | ◎ | |||
| 大麦 | ◎ | |||
| キヌア | ◎ | |||
| うどん | ○ | |||
| そば | ◎ | |||
| パスタ | × | |||
| 全粒粉パスタ | △ | |||
| 米粉パスタ | △ | |||
| 中華麺 | ○ | |||
| そうめん | ○ | |||
| 低糖質麺 | ◎ | |||
| 食パン | △ | |||
| バターロール | × | |||
| 全粒粉パン | △ | |||
| ライ麦パン | △ | |||
| クロワッサン | × | |||
| フランスパン | △ | |||
| ベーグル | △ | |||
| ナン | △ | |||
| ピザ生地 | × | |||
| 菓子パン・惣菜パン | × | |||
| 緑黄色野菜 | ◎ | |||
| 根菜類 | ◎ | |||
| さつまいも | ◎ | |||
| ジャガイモ | ◎ | |||
| 里芋・山芋 | ◎ | |||
| こんにゃく | ◎ | |||
| 春雨 | ◎ | |||
| タピオカ | △ | |||
| 餅 | △ | |||
| おかき・せんべい | × | |||
| ビスケット | × | |||
| ケーキ生地 | × | |||
| ドーナツ | × | |||
| パン粉 | × | |||
| シリアル | × | |||
| 寒天 | ◎ | |||
| フルーツ | ◎ | |||
| 缶詰フルーツ | △ | |||
| 純粋はちみつ | ○ | |||
| オリゴ糖 | △ | |||
| メープルシロップ | △ | |||
| ラカント | ○ | |||
| 砂糖 | × | |||
| 黒糖 | × | |||
| お酒 | × | |||
| 甘酒(米麹) | △ | |||
| 米粉 | × | |||
| 小麦粉 | × | |||
| 片栗粉 | × | |||
| 薄力粉 | × | |||
| 天ぷら粉 | × |
肉・魚・卵編
| 食材名 | ◎ | ○ | △ | × |
|---|---|---|---|---|
| 豚(ヒレ) | ○ | |||
| 豚(もも) | ○ | |||
| 豚(肩) | ○ | |||
| 豚(ロース脂あり) | △ | |||
| 豚(バラ) | △ | |||
| 豚ミンチ | △ | |||
| 鶏(もも) | ○ | |||
| 鶏(胸) | ◎ | |||
| 鶏(ささみ) | ◎ | |||
| 鶏(手羽元) | △ | |||
| 鶏(手羽先) | △ | |||
| 鶏(軟骨) | △ | |||
| 鶏(ミンチ) | ○ | |||
| 鶏(皮) | △ | |||
| 牛(赤身) | ○ | |||
| 牛(リブロース) | △ | |||
| 牛(バラ) | △ | |||
| 牛(ミンチ) | △ | |||
| 赤身魚(さば) | ◎ | |||
| 赤身魚(イワシ) | ◎ | |||
| 赤身魚(さんま) | ◎ | |||
| 赤身魚(ブリ) | ◎ | |||
| 赤身魚(アジ) | ◎ | |||
| 赤身魚(マグロ) | ◎ | |||
| 赤身魚(カツオ) | ◎ | |||
| 白身魚(タラ) | ◎ | |||
| 白身魚(ヒラメ) | ◎ | |||
| 白身魚(タイ) | ◎ | |||
| 白身魚(鮭) | ◎ | |||
| 白身魚(うなぎ) | ◎ | |||
| 卵 | ◎ | |||
| うずらの卵 | ◎ |
大豆・発酵食品編
| 食材名 | ◎ | ○ | △ | × |
|---|---|---|---|---|
| 納豆 | ◎ | |||
| 豆腐 | ◎ | |||
| 枝豆 | ◎ | |||
| ゆば | ◎ | |||
| 油揚げ | △ | |||
| きな粉 | ◎ | |||
| おから | ◎ | |||
| 豆乳 | ○ | |||
| 大豆ミート | ◎ | |||
| 味噌 | ◎ |
乳製品編
| 食材名 | ◎ | ○ | △ | × |
|---|---|---|---|---|
| ヨーグルト | ○ | |||
| 牛乳 | ○ | |||
| 加工乳 | △ | |||
| 強化乳飲料 | ○ | |||
| チーズ | ○ | |||
| バター | △ | |||
| クリーム | × | |||
| 練乳 | × | |||
| アイスクリーム | × |
加工肉・プロテイン編
| 食材名 | ◎ | ○ | △ | × |
|---|---|---|---|---|
| 水産練り製品 | ○ | |||
| 加工肉(ハム) | △ | |||
| 加工肉(ソーセージ) | × | |||
| 加工肉(ベーコン) | × | |||
| ホエイプロテイン | ○△ | |||
| ソイプロテイン | ○△ | |||
| カゼインプロテイン | ○△ |
調味料編
| 食材名 | ◎ | ○ | △ | × |
|---|---|---|---|---|
| 塩 | ◎ | |||
| 塩麹 | ◎ | |||
| 醤油 | ◎ | |||
| つゆ | △ | |||
| ポン酢 | ◎ | |||
| 黒酢 | △ | |||
| リンゴ酢 | ○ | |||
| ポッカレモン | ◎ | |||
| アマニ油 | ○ | |||
| エゴマ油 | ○ | |||
| サラダ油 | △ | |||
| オリーブオイル | ○ | |||
| ごま油 | △ | |||
| MCTオイル | ○ | |||
| 和風ドレッシング | × | |||
| 野菜系ドレッシング | △ | |||
| フレンチドレッシング | × | |||
| ごまドレッシング | × | |||
| ノンオイルドレッシング | △ | |||
| ソース系 | × | |||
| マスタード | × | |||
| ケチャップ | △ | |||
| マヨネーズ | × | |||
| 焼肉のたれ | × | |||
| すき焼きのたれ | × | |||
| トマトソース | ○ | |||
| マーガリン | × | |||
| パーム油(カレーなど) | × |
レトルト・インスタント編
| 食材名 | ◎ | ○ | △ | × |
|---|---|---|---|---|
| 牛丼 | △ | |||
| 親子丼 | ○ | |||
| 中華丼 | △ | |||
| 中華の素(回鍋肉など) | × | |||
| ペペロンチーノ | × | |||
| たらこ | △ | |||
| 明太子 | △ | |||
| カルボナーラ | × | |||
| トマトソース | ○ | |||
| バジル | ○ | |||
| カレー | × | |||
| ハヤシ | × | |||
| シチュー | × | |||
| スープ春雨 | ◎ | |||
| 卵スープ | ◎ | |||
| ワカメスープ | ◎ |
ふりかけ編
| 食材名 | ◎ | ○ | △ | × |
|---|---|---|---|---|
| 食べるラー油 | × | |||
| ごはんですよ | × | |||
| なめ茸 | ○ | |||
| メンマ | ○ | |||
| 焼鮭 | ○ | |||
| たらこ | ○ | |||
| 鶏そぼろ | ○ | |||
| 梅ふりかけ | ○ | |||
| 鰹ふりかけ | ○ | |||
| 海老ふりかけ | ○ | |||
| 納豆ふりかけ | ○ | |||
| のりふりかけ | ○ | |||
| しそひじき | ○ | |||
| わかめ | ○ | |||
| 塩こんぶ | ○ | |||
| 塩こんぶ(減塩) | ◎ | |||
| おかか | ○ | |||
| とろろ昆布 | ○ | |||
| ごましお | ○ |
惣菜編
| 食材名 | ◎ | ○ | △ | × |
|---|---|---|---|---|
| コロッケ | × | |||
| ビーフコロッケ | × | |||
| とんかつ | × | |||
| フィッシュフライ | △ | |||
| ポテトフライ | × | |||
| 唐揚げ | × | |||
| だし巻き卵 | ◎ | |||
| 焼き鳥 | ◎ | |||
| 焼き魚 | ◎ | |||
| とろろそば | ◎ | |||
| 温玉そば | ◎ | |||
| 冷やし中華 | ○ | |||
| 冷やしそうめん | ○ | |||
| きつねうどん | ○ | |||
| お寿司 | ◎ | |||
| 巻き寿司 | ◎ | |||
| オムライス | ○ | |||
| ナポリタン | △ | |||
| スパゲッティ | △ | |||
| お好み焼き | △ | |||
| カレー | × | |||
| 牛丼 | ○ | |||
| 親子丼 | ○ | |||
| ハンバーグ | △ | |||
| 肉まん | △ | |||
| シュウマイ | △ | |||
| 餃子 | △ | |||
| 幕の内弁当 | × |
デザート編
| 食材名 | ◎ | ○ | △ | × |
|---|---|---|---|---|
| ドーナツ | × | |||
| クレープ | × | |||
| ワッフル | × | |||
| シュークリーム | × | |||
| タルト | × | |||
| スフレ | × | |||
| プリン | △ | |||
| 杏仁豆腐 | ○ | |||
| ゼリー | ○ | |||
| どら焼き | △ | |||
| みたらし団子 | △ | |||
| カステラ | △ | |||
| おはぎ | △ |
お菓子編
| 食材名 | ◎ | ○ | △ | × |
|---|---|---|---|---|
| 豆菓子 | ○ | |||
| ナッツ類 | ○ | |||
| 干し芋 | ○ | |||
| 割れむき栗 | ○ | |||
| 甘酢イカ | ○ | |||
| こいわし | ○ | |||
| あたりめ | ○ | |||
| さきいか | ○ | |||
| スルメげそ | ○ | |||
| 焼かまぼこ | ○ | |||
| チーズかまぼこ | ○ | |||
| スライスサラミ | △ | |||
| ドライソーセージ | △ | |||
| BEEF | △ | |||
| おつまみ牛タン | △ | |||
| カルパス | △ | |||
| ドライフルーツ | ○ | |||
| プルーン | ○ | |||
| 米粉系お菓子 | △ | |||
| 小麦粉系お菓子 | × | |||
| ジャム | × | |||
| ピーナッツクリーム | × |
飲料水編
| 食材名 | ◎ | ○ | △ | × |
|---|---|---|---|---|
| 水 | ◎ | |||
| お茶 | ◎ | |||
| コーヒー(無糖) | ◎ | |||
| コーヒー(微糖) | ○ | |||
| コーヒー(ミルク) | △ | |||
| レモンティー | ○ | |||
| ストレートティー | ○ | |||
| ラテ | △ | |||
| 炭酸飲料 | × | |||
| 果実飲料 | × | |||
| 乳酸菌飲料 | × | |||
| 加糖飲料 | × |
補足
食品添加物は出来るだけ控える努力をしましょう!

食品添加物は、摂り過ぎると発がん性リスクが高まると言われております。健康作りはもちろんダイエッターにも悪影響を及ぼします。
しかし現代の食品に必ずと言っていいほど入っております。食品添加物を完全に避けるのはほぼ不可能に近いので、出来るだけ避ける努力をして未精製で未加工の食べ物を摂るようにしていきましょう。
- 保存料:食品の腐敗や劣化を防ぎ、保存性を高める。例:ソルビン酸。
- 人工甘味料:食品に甘味を付与する。例:キシリトール、アスパルテーム。
- 着色料:食品の色を鮮やかにしたり、色を調整したりする。例:クチナシ色素、食用黄色4号。
- 増粘剤、安定剤、ゲル化剤、糊料:食品に粘り気やとろみを与えたり、分離を防いだりする。例:CMC。
- 酸化防止剤:食品の酸化を防ぎ、風味や品質の劣化を抑制する。例:ビタミンC。
- 調味料:食品にうま味や風味を付与する。例:アミノ酸。
- 酸味料:食品に酸味を付与したり、pHを調整したりする。例:クエン酸。
- 香料:食品に香りをつける。例:バニリン。
- 栄養強化剤:食品の栄養価を高める。例:ビタミンC。
- その他:発色剤、漂白剤、防かび剤、乳化剤、膨張剤など、様々な目的で使用される。
プロテインは目的に合わせて飲みましょう!

【プロテインのメリット】
- 時短で安価にたんぱく質補給が出来る。
- 筋トレ後早急にたんぱく質補給が出来る。
- 筋肉量が増えやすくなる。
プロテインを飲むことで筋肉量が増えて代謝が上がり、痩せやすくなります。
ただしプロテインを飲み過ぎると、たんぱく質過多になり腸内環境悪化による便秘や乳糖不耐性による下痢、腎臓に負担をかけてしまうこともあります。
SALUGIAではダイエッターの方には筋トレ後にプロテインを飲み、それ以外は飲まないことを推奨しております。プロテインはあくまで栄養補助食品ですので、普段の食事は食べ物をベースとして栄養を取っていきたいです。
原材料名・栄養成分表を見る癖をつけよう!

食品選びで原材料名と栄養成分表を見ることはすごく大事です。
見る習慣をつけるとどんな食品が体に良いのか、カロリーが高いのかを判断することができるようになります。
一生役に立つことですので、ぜひチャレンジしてみましょう!
カロリー制限のやり方
1.カロリー計算で自分の食事量を把握しよう!
カロリー計算をすることで、自分が日々どのくらいの量を食べているのかが可視化され食事コントロールがしやすくなります。
【カロリー計算をするメリット】
- 体重増減の分析がしやすくなる
- 自分の適切な食事量が可視化される
- 栄養学や食事に関しての知識が身に付く
現代科学では1番体重に直結するのはカロリーと言われております。
確実に体重管理をしたい人や食事に関する知識を身に付けたい人は是非やってみましょう。
2.自分の活動代謝量を把握しよう!
カロリー計算とセットに把握しておきたいのが、自分の活動代謝量です。
1日の活動量から自分の食事摂取量が決まり、自分のライフスタイルに合わせてどのくらい1日でカロリーを消費するのかが異なります。また身体的機能に個人差があるので絶対数値ではないので参考までに把握しておきましょう。
3.月に何キロ痩せるかで摂取カロリーが決まります
1ヶ月に何キロ痩せるかで1日にどのくらいのカロリーを取れるかが決まります。
例えば1ヶ月で2キロ落とす場合、1日に可能な食事量から約480kcalを削減しなければなりません。この数値は絶対値ではありませんがおおよその目安になる数値ですので、参考にしてみてください。
また詳しいことはトレーナーにお聞きください。
SALUGIA推奨PFCバランス&たんぱく質摂取量

栄養バランスを整えるためにカロリーコントロールやPFCバランスを意識して食事管理をすることはすごく大切です。
以下の表はSALUGIA推奨のPFCバランスと目的別たんぱく質摂取量になります。ぜひ参考にして食事管理をしてみてください。
※この数値は目標達成を保証するものではございませんので、予めご了承ください。
| P | F | C | |
| ダイエット | 20% | 20~30% | 50~60% |
| ボディメイク | 25% | 20~25% | 50~55% |
| 健康作り | 15~18% | 25% | 57~60% |
| たんぱく質摂取目安量 | |
| ダイエット | 体重×1.5g |
| ボディメイク | 体重×1.8g |
| 健康作り | 体重×1.2g |

無料お試し体験実施中!
《LINEでお問い合わせ》